歴史の一番大事な意味について
『天皇の世紀』で河井継之助について書いた大佛次郎。大佛への追悼文で小林秀雄は河井継之助についてこう述べていた。
「歴史の動きが、よく見えて、身動きが出來なくなるほど、よく見え過ぎて、その為に歴史に取り殺されて了ふという事が、この人物には起きてゐる。といふのは、歴史の一番大事な意味が、人目には附きにくい、この人の内部で體得されてゐるといふ事である」
二十歳くらいの頃に出会ったこの「歴史の一番大事な意味」について今になって考えたくなった。それを体得するとはどういうことだろうか?わずか二ページの文章を箇条書きにするとこうなる。
・大佛が宿病の内に始まった天皇の世紀。他人事のようにいずれ蒸発さと笑う大佛を見て既に覚悟が決まってしまった人だと小林は感じる
・歴史の見方を生んだ謎としての歴史の正体に出会わねば歴史など面白いはずがない。歴史の魅力はその恐ろしさと表裏をなす。解こうとしなければ望むだけその謎の味わいは深くなる
・表題を見るたびに声をかけられる感じがした。その出所は紙背に没して、歴史家の無私な眼の動きがあった
・大佛がリアリズムの興趣に到達したことを明敏な彼なら追い込まれたと言うかもしれない。大佛の想像力は経験者たちの語る錯綜し矛盾した資料が生きていると言った意味合いの道を行く
・大佛は河井継之助の心の内側に入ろうと努める。継之助は歴史の動きが見え過ぎたために身動きも出来なくなり歴史に取り殺されてしまう。それは歴史の一番大事な意味をこの人が体得しているという事だ。この人の心は及び難く正直だ、と大佛は見ているように思われた
この文章から「歴史の一番大事な意味」の体得を推察するなら、謎としての歴史の正体が見え過ぎたために身動きが取れなくて取り殺された、ということになる。この謎としての歴史とは単に時勢というものではなく、歴史の見方を生んだもの、即ち自己ということになる(「考えるヒント」でも徂徠にとって歴史とは自己であるという文章がある)
この自己というものが説明しがたい性質を持っている。自己とは単に意識としての自分のことではなく、むしろ自分の持つあらゆる偶然の特殊性を乗り越えなければ得ることが出来ないその人の真の個性といった意味合いのものだった。継之助はそういう自己が見え過ぎていたために自己に取り殺された。それは即ち、及び難く正直な心を持った継之助の生き方が他に替えようがないほどに個性的な生き方だったということではないだろうか。それがおそらく「歴史の一番大事な意味」を継之助は体得しているということだと思う。
人生の意味について
小林にとって人生の意味を会得する、ということもそれと同様のことだったのではないだろうか。
『考えるヒント』の「物」という文章によれば、徂徠や彼の塾生の学問の目的は歴史の意味を明らかにすることであり、人生の意味を明らかにしようと努めることにあったという。ここでは歴史の意味と人生の意味はほぼ同じか不分離なものであるように思う。意味と同義の「義」は、人の志の大小に関する問題にして学びを要する難題であり、志とは「ヒューマニズム」という文章によれば人生の絶対的な意味に関するヴィジョンであるという。
つまり小林にとって人生(歴史)の意味を明らかにする際に重要なのはこのヴィジョンの大小に関係する、ということらしい。
ヴィジョンという言葉は「プルターク英雄伝」では世の中はどんなに変わっても人間は変わらないという一般の生活人の歴史意識、感慨または芸術家のヴィジョンとして述べられている。
「天という言葉」でもヴィジョンについて言及している箇所がある。福沢諭吉は文明の歴史的個性を見て信じ、この無私なヴィジョンのうちにだけ活路を見出した。このヴィジョンの力は、生活力の強い明敏な常識を持った人々が、その個人的な窮境を打開するのと同じやり方であり、ヴィジョンによって活路を見出し一歩踏み出すという自覚による行為こそ無私の精神だ、としている。福沢の著作に感じられる無私とは、直視されかけがえのない実相で充満していることとも述べている。
歴史の意味や価値は、起こったことの特殊性に、生きていた人間の個性に固く結ばれていると「物」で述べている。また歴史の意味という学問を学ぶことは芸を学ぶことと同じだと言う。芸や技術を得るには忍耐強く時間に俟つことが必要であるため、誰もが持つ歴史意識としてのヴィジョンを当人にとっての人生の絶対的な意味に関するヴィジョンにまで錬磨しそれを得るにも同様の苦労と忍耐が必要になる、ということだろうか。
「徂徠」という文章では、徂徠の思想はその剛毅な個性という一点に向かっている趣があり、くどさにこそその人の良心、確信、人格につながり、自覚の深さが豪さにつながると述べている。ヴィジョンを得るとはそういう個性を得るということと呼んでもいいのだろう。それが小林にとっての人生の意味を会得するということなら、それは心理学者ユングの言う個性化過程と似ているようにも思った。ユングも個性化過程を得ることでその人の意識領域が広がり人生の態度が変わると述べている。ユングが無意識と言うところを小林は精神と呼んでいる違いはあるものの、どちらも個性化過程で起こる普遍的な経験について言及し、小林は孔子の天命を知る、あるいは天に知られることを言い、ユングはヌミノースと呼んだ。
そういう人生の意味、個性、ヴィジョンを得る道について分かり易く一口に言ったのが「徂徠」の学者は身に取りて思うことに努めればいい、我が身にとって思うこれという確かな物があればそれで不足はない、それが学問の道だ、という文章なのだろうと思う。それは別に学者に限らず一般の生活人でも自分の人生を充実させたい人は自分にとって切実なこと、本当に心から面白いと思ったこと好きなこと怒ったことなどに集中すればいい、という事ではないかと思う。これを「無私の精神」で述べられている小林の批評の仕事に当てはめれば、批評家が対象として取り上げた経験的事実は必ずしも任意に選んだ事実ではなく、多くの場合批評家の生活環境が問題として強制する事実であり、この現在の経験的事実の動きは現在の価値判断を迫るため、批評の方法はこの対象の性質に直接に規定されている。従ってその方法は実践的なものでなくてはならない、ということになるのだろう。
大佛が天皇の世紀を執筆したのも宿病という彼の生活環境が強制する事実と切り離せない面があったのだろう。宿命に対して既に覚悟か決まってしまった大佛が宿命と対峙してそれに殉じた継之助を取り上げたのも任意ではなく必然と呼んでいいのかもしれない。長年のそのような経験を重ねてリアリズムの興趣に到達した大佛の無私の眼は、継之助の及び難い正直さを捉える。ここに継之助の豪い個性を視る、即ちそれは大佛が歴史の意味を体得することに他ならない。それはプラトンがソクラテスの個性を捉えたことと同様の経験であり、そうして出来たプラトンの作品は現代の人から見ても、ソクラテスとプラトンの思想の区別はほぼつかないか、両者が同じでも全く構わないといった説得力を作品から受け取る。
『峠』で継之助について書いた司馬遼太郎は、『峠』の前に『英雄児』という短編を書いている。そこでは継之助の選択によって多くの領民が戦争に巻き込まれ、理不尽に殺戮されたため継之助は死後も人々に恨まれたという負の面を取り上げて文を結んでいた。しかし、その後に司馬はまるで自分が書いたものを払拭するかのように改めて長編の『峠』に取り掛かった。取り掛かったというより、追い込まれて取り掛からざるを得なかったのではないだろうか。それは司馬が歴史の一番大事な意味の体得に努めていなければ起こらなかっただろう。

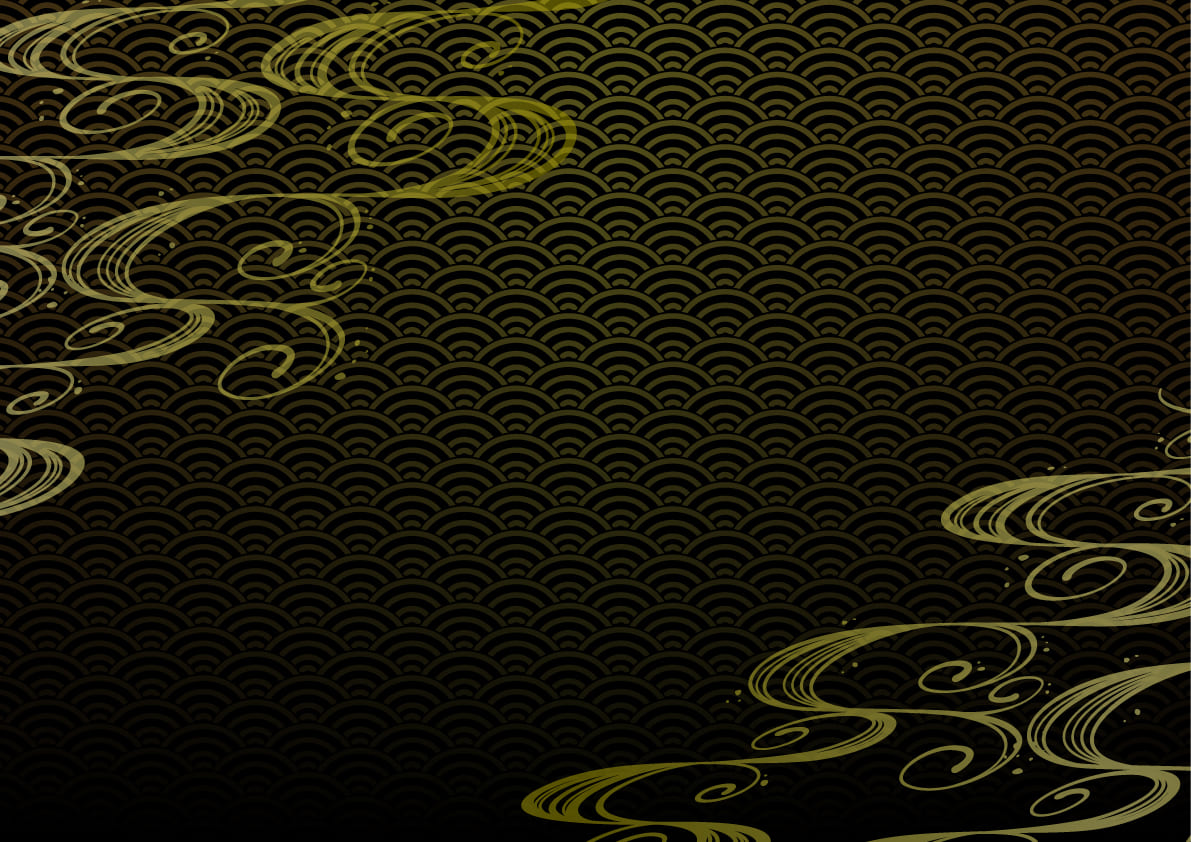


コメント