
「何か」の正体は原生命や原人間、あるいは心の中心や全体などを表す「自己」元型と呼ばれるものだったのではないかという一説

なんぞやそれ?
「何か」は作中ではムカデとも呼ばれた光る生物だった。クルーガーが有機生物の起源という説に触れ、137話の生物の話の関連でDNAやハルキゲニアなどの古カンブリア紀の描写があることから、その「何か」とは人間などの生物の先祖をイメージした存在と思われること、こうした推測はすでに読んだ人たちの間でもされていた。しかしそうした推測以上のことはほとんど謎でもあった。
『進撃の巨人』諫山創 講談社 137話「巨人」
そこで個人的に、ユミルが二千年前に出会った巨人の起源との出会いがグリム童話に似ていたり、また座標や道の時間のない世界が人間の見えない心の世界に似ていたりすると思ったため、この正体は心の根底と起源を表すものでもあるのではないかと思った。ユング心理学ではそれを遺伝で誰にでも備わっている「元型」としている。それは「原初の時代からこの惑星で営まれてきたあらゆる経験を代表している(『タイプ論』432ページ)もので、その人個人の意識や思い出より前から常に存在している無意識の内容のことだった。
仮にユミルと「何か」の接触が、ユミルの心の中の体験でもあったと見ることも可能なら、ある意味それは一人の人間が自分の先祖や起源と出会うということの描写でもあったのかもしれない。ユミルの始祖の力にも巨人の素材だけではなく、記憶や誰かの意思など心に関することも道を通して送る能力があった。
ユミルと巨大な木
ユミルが「何か」と出会ったあらすじ
『進撃の巨人』諫山創 講談社 122話「二千年前の君から」
これと似た話にこういうのがある。
グリム童話「ガラス瓶の中の化け物」
また精神科医のユングの診察した患者の夢にも似ていると思われるものがあった。
「ある学生の夢」
この夢を見た学生は激しい感情を覚えて即座に自然科学の勉強を始めたという。ユング心理学ではこの夢は元型のような性質を持つ「大きな夢」ということだった。ユミルが「何か」に出会った話も、このような「大きな夢」の意味があったのではないだろうか。
ユングの話では、森は妖精物語では魔法の起こる暗くて目に見えない神秘的な場所を表し、それは人間の心の深層である無意識を表すという。円い池とその中の輝く物体、クラゲは無意識の中の「自己」という元型を表すらしい。
「自己」は意識と無意識の中心であり、同時にそれらを含む心の全体のことだという。学生が悩みを抱えて意識が行き詰まりを感じている時など、またその人の選択がその本性から明確に誤っている場合などには「大きな夢」によって全体のイメージを意識に認識させることもあるのだろう。
しかし基本的に意識の世界が無意識の世界に妨げられると自我が適応できなくなり精神病などになる。逆に意識が自分の世界のみを信じて無意識を排除しても、意識が思い上がって神経症などになる。意識と無意識のどちらも過大評価も過小評価もせず、心にとって大事な一つの機能として把握することが必要なのだろう。
「自己」はまた昔から「あらゆる生物に内在している神的な秘密の別のある一面」として現れていて、古代や中世の西洋では賢者の石や原生命、原人間やホムンクルス、またはメルクリウスとも呼ばれていたという。
メルクリウスはグリム童話に出てきた魔物の名前でもあり、それは巨木の半分ほどの大きさもあった。学生の夢の話からこの童話を推測するなら、メルクリウスという巨人と大木と宝は同じで「自己」という元型を表し、それならユミルの話の大木と泉と「何か」も同じで「自己」を表すと考えられる。
「自己」は人間の最大の宝であり、人を癒すものとされていたため、「救済者」「大地の神」ともされていた。ユミルはマーレ政権下では「大地の悪魔」と契約した「悪魔の使い」と伝えられ、エルディア帝国時代は「神がもたらした奇跡」と伝えられた。エルディア部族や後の帝国時代から見ればそれは「大地の神」とされたと見るのが妥当と考えられる。また、その歴史の挿絵にはユミルが智慧の実を悪魔から授けられているようにも見えて、聖書の創世神話を思わせる。悪魔は西洋では蛇として表されることが多いため、この悪魔も聖書の楽園の蛇にあたるだろうか。
『進撃の巨人』諫山創 講談社 86話「あの日」
この蛇は古代や中世では生命の木の化身と見られたという。挿絵にもそれらしき木が見られる。「何か」のいたところも巨木であり、座標も光り輝く大木の姿をしていた。全てのユミルの民は目に見えない何かでつながっていて、それは道と呼ばれる世界だった。その道の全てが交わる場所が座標と呼ばれた始祖の巨人だった。
『進撃の巨人』諫山創 講談社 120話「刹那」
これらが「自己」を表すなら、道の世界とは無意識の世界を表すとも考えられる。無意識は個人の記憶以前の始原、遠い先祖や動物たちの心をも基盤にしていた。個人を超えているために、他者ともシンクロしてつながることがあることも現実では少なくない。永遠でもあり一瞬でもある道の世界には死んだはずの人たちがいてもそこは死後の世界ではなかった。彼らは道でつながっている人たち全体の記憶の存在ではないだろうか。
ユミルは座標から全てのユミルの民の記憶や意思に干渉できるという。これも無意識から人々の意識に干渉しているという元型の性質に合うことは合う。しかし進撃の巨人は物語であって心理学ではないため、そこまできっちり合わせる必要もない。
無意識の元型的イメージは人間の本能の力を解放するともしている。学生が「大きな夢」によって全体の状況の認識を助けられたのもそうした効果のためだった。本能は人間が普段生活をするために抑えられたり低い評価をされている動物的なものでもあり、自己の元型もそうした根底の本能の深みで捉えられるために、中世西洋では蛇などの脊椎動物の姿で表されることが多かった。ヒンドゥー教のクンダリニーという蛇も同様に体内の根源的エネルギーを意味するという。「何か」がハルキゲニアのような姿だったのもそのような意味ではないだろうか。実際のハルキゲニアの体長は1~5cmと小さく、節足動物であり脊椎はないらしい。作中のムカデ呼びはその意味では正確だった。実際の脊索動物の共通祖先はナメクジウオやピカイアに似たものとされているらしい。しかし進撃の巨人で表されている生物の起源がある種の本能にも関連するなら、それは古来から魚、蛇、竜、リヴァイアサンなどとして姿を変えて表されてきたように「幻、夢想」を意味するハルキゲニアでもいいかもしれない。
蛇はまた脱皮するという現象から再生や若返りのイメージが古来からあり、心理学ではそれを自己の元型の意識と無意識の統合から同じ意味として捉えていた。最近ナショナルジオグラフィックで紹介された古代エジプトのナマズも再生の象徴とされていた。ナマズは冥界の暗闇の中での導き役でもあったという。おそらくユミルにとって「何か」と出会うというのも暗闇の中で光を得ることで、それは自分のまだ知らない自分に出会うという生まれ変わるような内なる体験のことだったのではないだろうか。
仮にそうなら、それはミカサが生きている奇跡を実感して戦う決意をしたことでアッカーマンの覚醒が起こったことに似ているかもしれない。あるいはそれはユミルの名を騙ったもう一人のユミルが他の誰でもなく自分自身として生きていくことを決心した心境にも似ているだろうか。この時の風景はどこか座標の世界を思わせる。こうした本能の解放によって自分が生まれ変わったかのような経験を表現したものが「何か」との出会いや座標という形になった、とも考えの一つにあってもいいのではないだろうかと思った。
『進撃の巨人』諫山創 講談社 6話「少女が見た世界」 89話「会議」
おまけ ユミルとミカサ

最終話を読むとユミルはミカサを待っていたということだけど、どうしてミカサだったの?

ユミルと同じ意思を持っていたエレンもユミルの考えはわからないと言ってるんだよな…その上で
ユミルが愛に未練があったような描写がされていることと、最終話のフリッツ王の描写から愛の清算がミカサの選択によってされて巨人の力が世界から消滅したように見える。
ユミルは自由と愛の板挟みで巨人の消滅を願いながら巨人を作り続けるという矛盾した行動をとっていた。ミカサもエレンと世界との板挟みで苦しんでいた。
クルーガーがグリシャを後継者に選んだのは、自分と似た境遇であることと同時に罪の意識や後悔を抱えていたことが最大の理由だった。それと似ているように思う。悩みが似ていて、かつミカサも罪や後悔を抱えていたからこそ、二千年前からそれを抱えていたユミルは選んだのだろうか。
どんなに後悔しても過去は変わらない。しかしそうした事実があったからこそ「今がある」と考えることは出来る。ミカサがユミルに最後に言った台詞は、そうしたマイナスとプラスの両方の評価になる。こうした適切な認識はユミル同様に苦しんでいたミカサが自分自身を救うことにもなったのかもしれない。
エルヴィンは、人が死ぬことに意味はない、しかし死者を想い意味を与えるのは生者だけと言った。進撃の巨人には人の死を決して美談にはしないという固い意志が貫かれていたのと同時に、そのように人の命を意味や価値あるものにするという考えも同時に見られた。ユミルが二千年前から求めて進み続けたものは自身のそれで、それがミカサの選択によってもたらされたのなら、それは進み続けたユミルだからこそ得られた「何か」との出会いでもあったかもしれない。
参考文献 『アイオーン』C・G・ユング/M.L.フォン フランツ/野田倬(翻訳) 人文書院 1990年11月
参考サイト「精霊-メルクリウス(1/3)」Barbaroi!


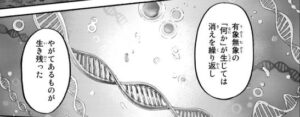










コメント